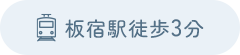- いつの間にか骨折!?
骨粗しょう症とはどんな病気? - 骨粗しょう症の主な原因
- 骨粗しょう症で骨折しやすい部位
- 骨粗しょう症になりやすい体質や傾向(性別・年齢など)
- 骨粗鬆症の診断と検査
- 骨粗しょう症の治療
- 骨粗しょう症でも長生きできる?
寿命への影響 - 骨粗しょう症予防には日光浴が大切!
効果的な時間とポイント
いつの間にか骨折!?
骨粗しょう症とはどんな病気?
 骨粗しょう症とは、骨密度が低下、骨質が悪くなることで、骨折をしやすくなる病気です。
骨粗しょう症とは、骨密度が低下、骨質が悪くなることで、骨折をしやすくなる病気です。
転倒したり、よろけて手をついたり、場合によっては大きな咳やくしゃみといった程度の衝撃でも、骨折することがあります。また、自分で気づかないうちに脊椎(背骨)の圧迫骨折が起こる“いつの間にか骨折”、骨折が連鎖する“ドミノ骨折”なども見られます。
特に腰椎や大腿骨の骨折は、完治するまで活動範囲が著しく制限されるため、治療期間中の筋力の衰え・可動域の減少によって介護が必要になる・寝たきりになるといったリスクもはらみます。
骨折をしてからではなく、骨折をする前に骨粗しょう症を発見すること、あるいは予防することが大切です。
骨粗しょう症は、50代後半以降に見られることが多い病気です
骨粗しょう症は、加齢、更年期の女性ホルモンの減少などが原因となるため、基本的に年齢を重ねた人ほど、発症率が高くなります。
平均すると、誰でも50代後半以降は、骨粗しょう症になっている可能性があるとお考えください。特に女性は、更年期の女性ホルモンの減少によって、40代で発症するケースも少なくありません。
骨粗しょう症の主な原因
骨は、常に吸収と形成を繰り返しています。吸収量が形成量を上回ることで、骨密度の低下・骨質の悪化が進み、骨粗しょう症を発症します。
加齢
骨量は通常、10代後半から20歳くらいでピークを迎え、その後徐々に低下していきます。
閉経(女性)
女性の場合、閉経を境に急激に女性ホルモンの量が減少します。骨の新陳代謝が悪くなることで、骨密度が低下したり、骨質が悪くなったりします。
生活習慣の乱れ
カルシウムやビタミンの不足、運動不足、喫煙、飲酒といったことも、骨粗しょう症の原因となります。無理なダイエットによる栄養不足が原因になることもあります。
疾患・薬の副作用
関節リウマチや糖尿病、副甲状腺機能亢進症の合併症として、あるいはステロイドの長期内服が原因となって、骨粗しょう症を発症することがあります。
骨粗しょう症で
骨折しやすい部位
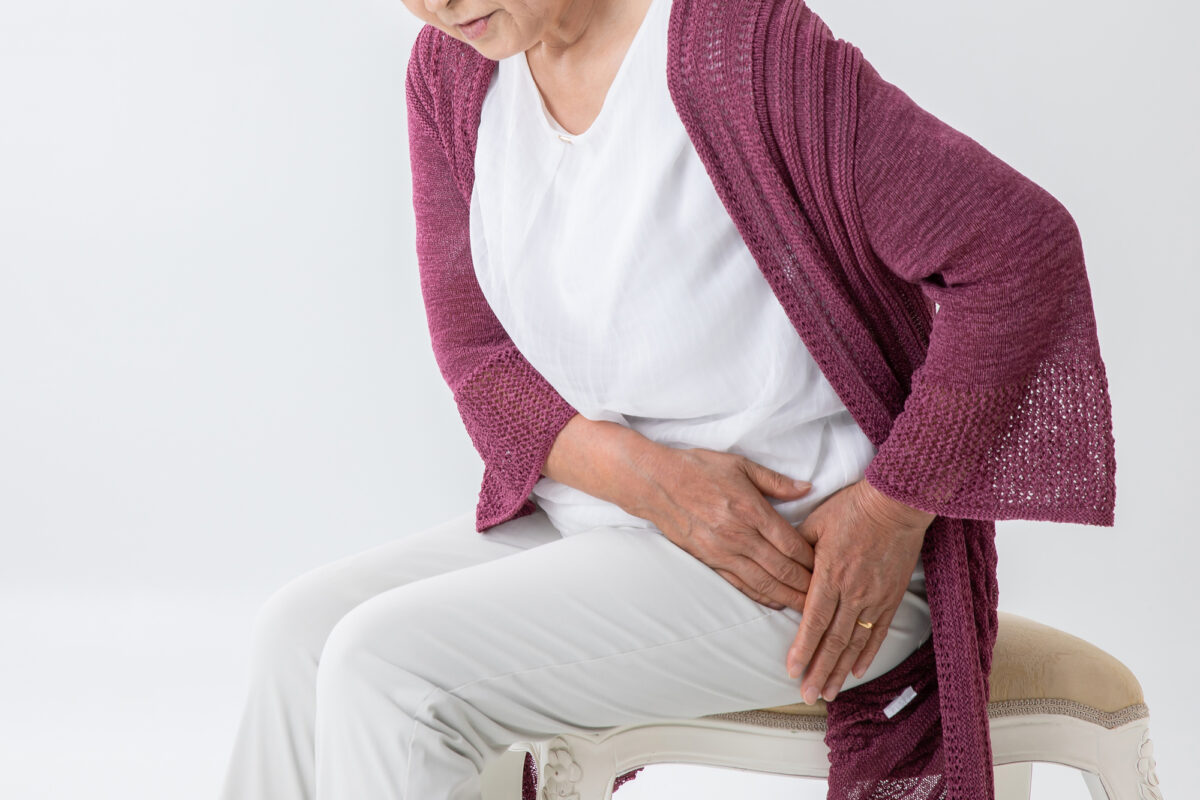 骨粗しょう症を原因として骨折しやすいのは、以下のような部位です。
骨粗しょう症を原因として骨折しやすいのは、以下のような部位です。
特に注意が必要なのが、背骨や脚の付け根の骨折です。治癒を待つあいだに筋力や柔軟性が低下し、特にご高齢の方にとって、歩行困難、寝たきりなどのきっかけになりやすい骨折となります。
- 腕の付け根(上腕骨)
- 手首(橈骨)
- 背骨(脊椎)
- 脚の付け根(大腿骨近位部)
骨粗しょう症になりやすい体質や傾向(性別・年齢など)
女性は特に注意が必要
骨を守る働きを持つエストロゲンという女性ホルモンは、閉経を境に急激に減少します。
骨粗しょう症患者の約8割を、女性が占めます。
年齢とともに
リスクが上がる
骨密度は通常、年齢を重ねると共に低下していきます。50代後半からは、誰しもが骨粗しょう症になるおそれがあります。
体格や体質による影響
痩せ型の方、骨粗しょう症の血縁者がいる方は、骨粗しょう症の発症リスクが高くなります。
食事や生活習慣も関係
カルシウムや各種ビタミンの不足、運動不足、喫煙・飲酒習慣は、骨粗しょう症のリスクを高めます。
これらに該当する方は、骨粗しょう症リスクが高くなるため、早めに骨密度の検査を受けたり、生活習慣を改善することで、早期発見と予防に努めましょう。
骨粗鬆症の診断と検査
問診・診察
問診では、骨折や疾患の既往歴、その他の症状、服用中の薬、生活習慣、閉経時期などについてお伺いします。また、若い頃の身長が分かる場合は、現在の身長と比較します。
骨密度検査
エックス線を用いるDXA法、MD法、超音波診断装置を使う方法などにより、骨密度を測定します。当院では、高精度で一番信頼度の高いDXA法を実施します。
レントゲン検査
胸椎や腰椎の骨折や変形の有無の確認、他の疾患との鑑別に役立ちます。
血液検査・尿検査
骨の吸収・形成の活性度を表す骨代謝マーカーを調べます。
骨粗しょう症の治療
主に、以下のような治療を行います。
治療期間中は、治療の効果を確かめ、より良い治療へとつなげていくため、定期的に骨密度検査・血液検査を行います。
薬物療法
カルシウムやビタミンD、ビタミンK、骨吸収抑制剤、骨形成促進剤などを使用します。
食事療法
栄養バランスの良い食事を基本とします。特に、カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、タンパク質を十分な量、摂ることが大切です。
運動療法
運動は、骨形成を促進したり、低下した食欲を取り戻すのに有効です。また、筋力やバランス感覚が改善することで、転倒防止にも役立ちます。
骨粗しょう症でも長生きできる?寿命への影響
 骨粗しょう症が直接、寿命を縮めるということはありません。
骨粗しょう症が直接、寿命を縮めるということはありません。
しかし、腰や下肢の骨折によって介護が必要になったり、寝たきりになったりすると、活動量が大きく低下し、肺炎や血栓症のリスクが高まり、間接的に寿命が短くなるということはあります。
こういったことを避けるためには、骨粗しょう症にならないことがまず大切になります。また、骨粗しょう症になった場合にも、適切な治療を行い骨折を避けることができれば、寿命が短くなるという心配はほとんどありません。
骨粗しょう症にならないこと・早期に適切な治療を行うことは、QOLを維持し毎日を安心して過ごすことにもつながります。骨粗しょう症のリスクが高い方、骨粗しょう症かもしれないと感じる方は、放置せずお早目に当院にご相談ください。
骨粗しょう症予防には
日光浴が大切!
効果的な時間とポイント
簡単に取り組める骨粗しょう症予防に、日光浴があります。日光浴によって、カルシウムの吸収を助けるビタミンDを体内で合成することができます。
夏であれば木陰などで1日15~30分程度、冬であれば日なたで30~60分程度の日光浴がおすすめです。
- カルシウム:牛乳、ヨーグルト、小魚、緑黄色野菜など
- ビタミンD:鮭、いわし、きのこ類、そして日光浴
- たんぱく質:肉、魚、大豆製品、卵
これらの栄養素をバランス良くとることで、骨を強くし、骨密度の低下を防ぎます。
適度な運動を続ける
運動は骨に適度な刺激を与え、骨密度を保つのに役立ちます。
ウォーキング、軽い筋力トレーニング、体操など、自分に合った運動を無理なく継続することがポイントです。
喫煙と過度な飲酒を控える
喫煙や過度な飲酒は骨の健康に悪影響を与え、骨密度低下のリスクを高めます。
骨粗鬆症予防のためには、これらの習慣を見直すことも重要です。