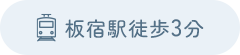- 水虫になると足が臭い!?
水虫(白癬:はくせん)とは - 水虫の主な症状(部位別)
- 水虫はうつる?原因と感染経路
- 水虫になりやすい人の特徴
(年齢・性別・生活習慣) - 水虫の検査・診断
- 水虫の治療法
- 水虫は治っても繰り返す!?
治療期間の目安と予防法
水虫になると足が臭い!?
水虫(白癬:はくせん)とは
 水虫とは、足などの皮膚に白癬菌が感染して起こる病気です。
水虫とは、足などの皮膚に白癬菌が感染して起こる病気です。
感染した皮膚が荒れたり、雑菌が繁殖することで、嫌なにおいの原因となります。
水虫の主な症状(部位別)
水虫は、発症する部位によって症状が異なります。
足(水虫の最も多い部位)
もっとも多いのが、足での感染・発症であり、これを「足白癬」と言います。
足白癬は、さらに以下のように分類されます。
趾間型(しかんがた)
足指のあいだの皮膚が白くふやける、皮が剥けてジュクジュクするといったケースがよく見られます。多くの場合、激しいかゆみを伴います。
小水疱型
(しょうすいほうがた)
土踏まず、足の側面などの皮膚に小さな水ぶくれ、激しいかゆみを伴います。水ぶくれが破れると、ただれ、皮むけなども生じます。
角質増殖型
(かくしつぞうしょくがた)
足裏、かかとなどの皮膚が、硬く厚くなる水虫です。皮膚がひび割れることもあります。かゆみは、比較的軽度です。
手
手に発症した水虫です。足の水虫から白癬菌がうつり、発症するケースがほとんどです。皮膚の肥厚、皮むけなどの症状を伴います。多くは、片手に発症します。
体(体部白癬)
体部白癬では、赤い円型の発疹、盛り上がり、かゆみといった症状が見られます。
頭(頭部白癬)
頭部白癬では、ふけ・かさぶた、脱毛などの症状が見られます。多くは、子どもに発症します。
股(股部白癬)
股部白癬では、股間・太ももの内側に、赤み・かゆみを伴う発疹が見られます。「いんきんたむし」とも呼ばれます。主に、男性に起こる水虫です。
水虫といえば足にできるものが有名ですが、上記のように、全身のどこにでも発症します。激しいかゆみを伴うことが多く、ご家族などにもうつしてしまうことがあるため、気づいた時にはお早目にご相談ください。
水虫はうつる?
原因と感染経路
原因となる菌
水虫の原因は、白癬菌の皮膚の感染です。白癬菌はカビの一種であり、角層・爪・毛髪などに含まれるケラチンを好みます。また、夏場・蒸れた靴の中など、高温多湿の気候・環境で繁殖します。
主な感染経路
感染者の皮膚と直接、または物を介して間接的に触れることで感染します。
不特定多数の人が裸足で歩くプール・銭湯の床、家族内でのスリッパ・バスマットの共有などが、主な感染経路になると言われています。
水虫になりやすい人の特徴
(年齢・性別・生活習慣)
水虫は、誰もがかかる可能性のある皮膚疾患です。ただ、その中でも特に感染・発症リスクが高い人がいます。
年齢
通常、加齢と共に皮膚のバリア機能が低下します。そのため、40歳以降の発症が目立ちます。
性別
男女別では、水虫は男性に多い傾向が認められます。これは、男性の方が汗・皮脂の量が多いこと、蒸れやすい革靴を履く機会が多いことなどが影響しているものと思われます。
体質・生活習慣
汗をかきやすい体質の方
白癬菌は高温多湿の環境で繁殖しやすいため、汗をかきやすい体質の方は、そうでない方よりも水虫の発症リスクが高くなると思われます。
足の指が密着している人
足指のあいだが蒸れやすいため、白癬菌が繁殖しやすい環境となります。
通気性の悪い靴を履くことが多い方
革靴、ブーツなどの通気性の悪い靴は、中が高温多湿であるため、水虫の大きなリスク因子になります。
家族に水虫患者がいる方
スリッパ、バスマットを共有している場合、白癬菌がそれらを介してうつる可能性が高くなります。
その他のリスク
スポーツや仕事の関係で同じ靴を履いたまま長時間過ごすこと、糖尿病などによる免疫力の低下なども、水虫のリスク因子となります。
汗をかいたら着替える・シャワーを浴びる、通気性の良い靴を選ぶ、革靴は2足用意し交互に履く(履かない方を乾かす)といった工夫により、水虫の発症・家族内の感染を防ぎましょう。
水虫の検査・診断
水虫が疑われる場合には、以下のような検査を行い、診断します。
直接鏡検KOH法
ピンセットやメスなどで、角質・水ぶくれ・爪・毛を採取し、そこに苛性カリ(KOH・水酸化カリウム溶液)を滴下し、顕微鏡で観察する検査です。薬液によって組織が溶かされることで、白癬菌の有無を確認しやすくなります。
培養検査
白癬菌の種類の特定が必要となった場合には、培養検査を行います。白癬菌には、紅色菌(トリコフィートン・ルブルム)、毛瘡菌(トリコフィートン・メンタグロフィーティス)といったようにいくつかの種類があります。
水虫の治療法
日本皮膚科学会のガイドラインに従い、以下のような治療を行います。
外用薬(塗り薬)
 足・手の水虫の場合は、塗り薬を使用します。ルリコナゾールやラノコナゾール、ケトコナゾール、ビホナゾール、エフィナコナゾール、塩化テルビナフィンなどから、状態に合わせて選択します。塗り薬は、1日1回、使用します。
足・手の水虫の場合は、塗り薬を使用します。ルリコナゾールやラノコナゾール、ケトコナゾール、ビホナゾール、エフィナコナゾール、塩化テルビナフィンなどから、状態に合わせて選択します。塗り薬は、1日1回、使用します。
内服薬(飲み薬)
 爪水虫(爪白癬)を合併しているケースでは、内服薬を使用します。テルビナフィン、ホスラブコナゾール、イトラコナゾールなどから、状態に合わせて選択します。
爪水虫(爪白癬)を合併しているケースでは、内服薬を使用します。テルビナフィン、ホスラブコナゾール、イトラコナゾールなどから、状態に合わせて選択します。
水虫は治っても繰り返す!?
治療期間の目安と予防法
水虫は、一度治っても再発しやすい皮膚の病気です。
その原因と治療期間の目安、再発を防ぐ方法などについて、ご紹介します。
水虫が繰り返しやすい理由
治療によって症状が落ち着いた時点では、まだ高確率で白癬菌が存在します。治ったと自己判断し治療を中断してしまったり、感染予防を怠ると、再発する可能性が高くなります。
また、家族内でピンポン感染してしまうケースも少なくありません。
治療期間の目安
 水虫の治療では、白癬菌が残らないよう、症状が落ち着いてからも、1ヶ月以上は外用薬の使用を継続することが推奨されています。足の水虫の場合は、治療期間が3ヶ月以上に及ぶこともあります。
水虫の治療では、白癬菌が残らないよう、症状が落ち着いてからも、1ヶ月以上は外用薬の使用を継続することが推奨されています。足の水虫の場合は、治療期間が3ヶ月以上に及ぶこともあります。
必ず、医師の指示をお守りくださいますよう、お願いします。何かご不明の点がございましたら、お気軽にお尋ねください。
再発を防ぐ予防法
足を清潔かつ
乾燥した状態に保つ
毎日、お風呂で足をきれいに洗いましょう。またその後、十分に水気をとってください。特に指のあいだは、しっかりと乾かしましょう。
なお、白癬菌が足などに付着しても、24時間以内に洗い流せば、水虫の発症の心配はないとされています。
通気性の良い靴・
靴下を選ぶ
足などを、高温多湿の環境に置かないことが大切です。通気性の良い靴・靴下を選ぶ、お仕事などでやむを得ず1日革靴を履いた場合は翌日は乾かす(2足用意しておくと便利です)といった工夫をしましょう。五本指のソックスもおすすめです。
共有物の管理に注意する
スリッパ、バスマットなどは、たとえご家族内であっても共有は避けましょう。
早めの治療と
受診を心がける
かゆみ、皮むけなどの症状に気づいた時には、お早めに皮膚科にご相談ください。面倒なように思えても、家族内でのピンポン感染を防ぐためにも、その都度、しっかりと治療を受けましょう。